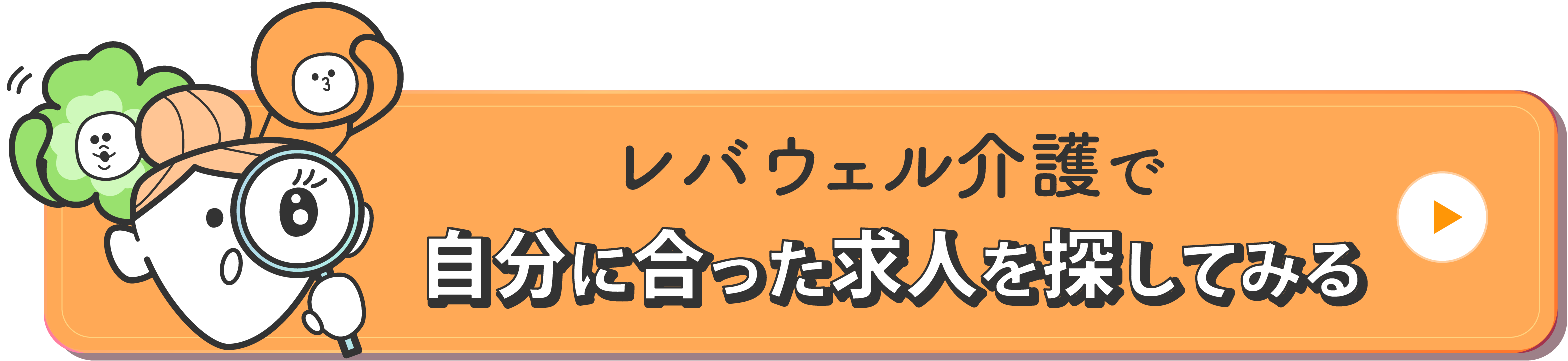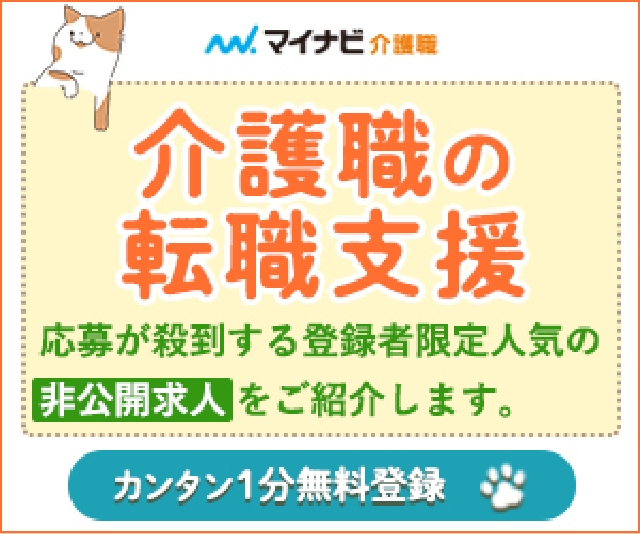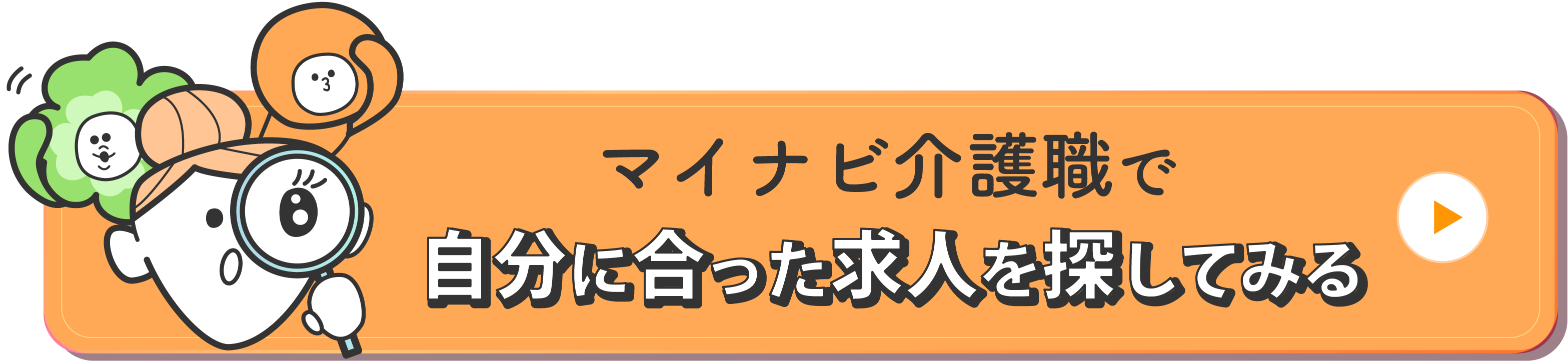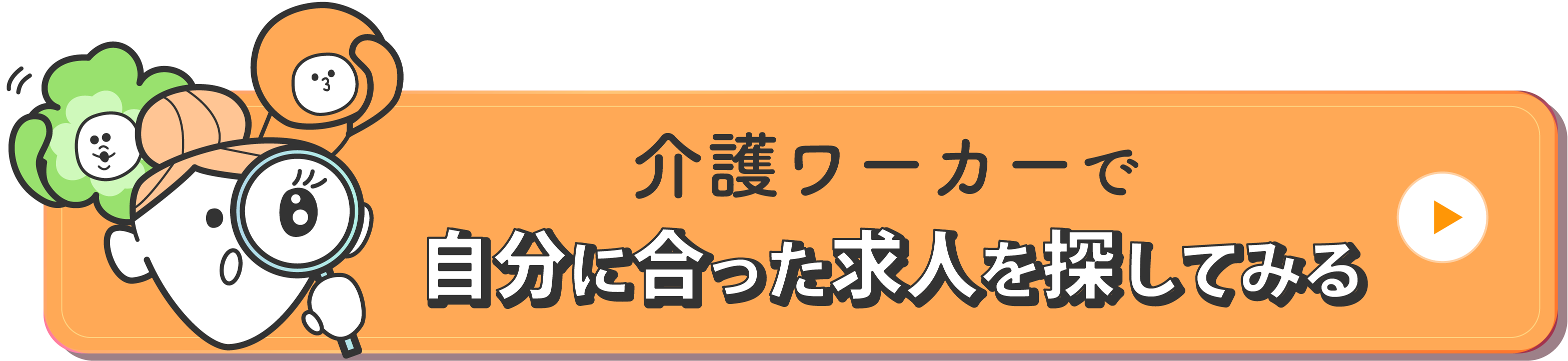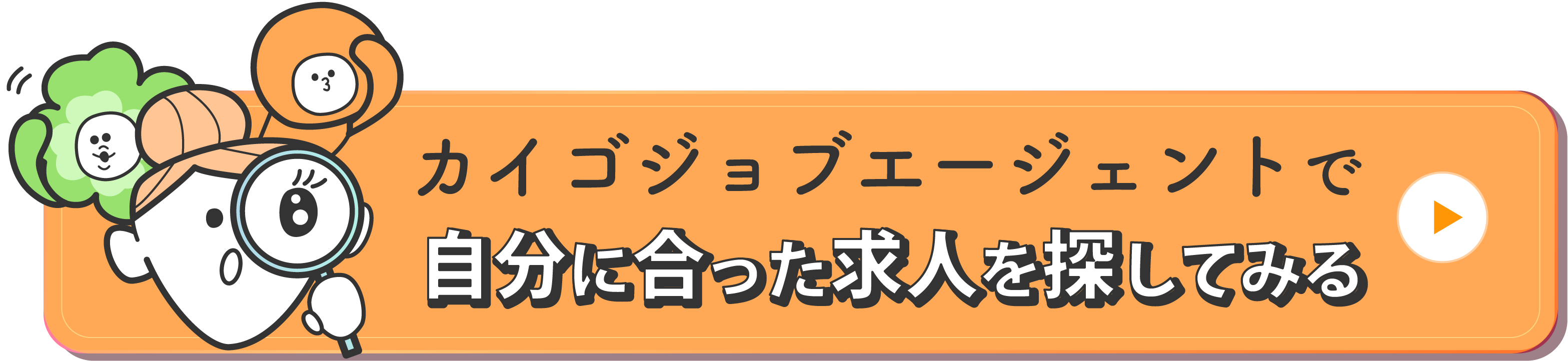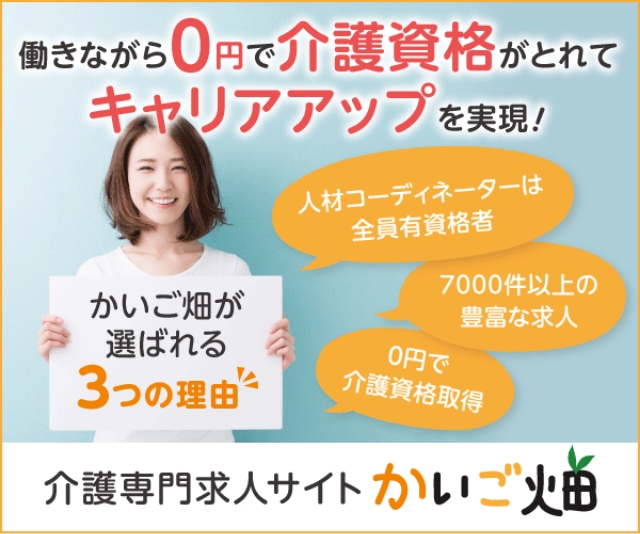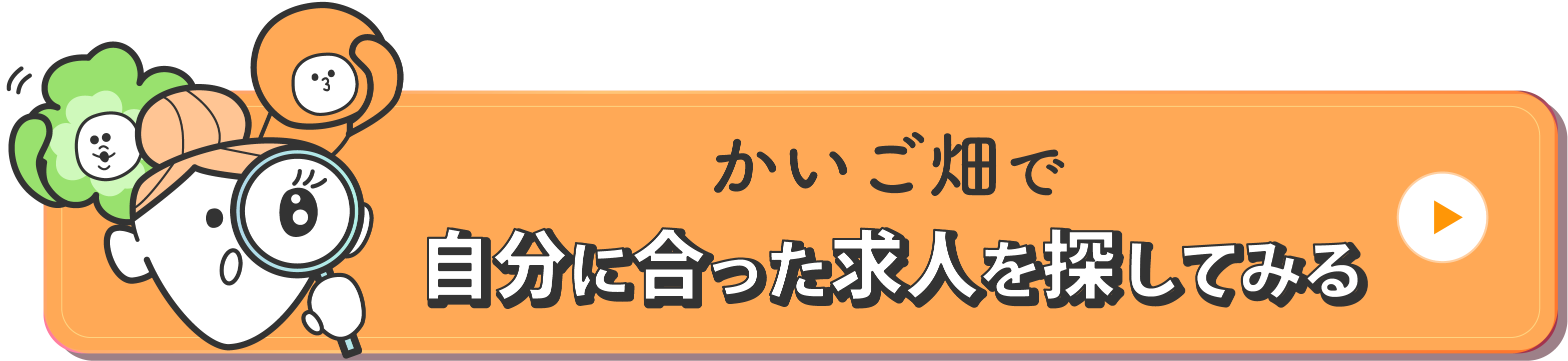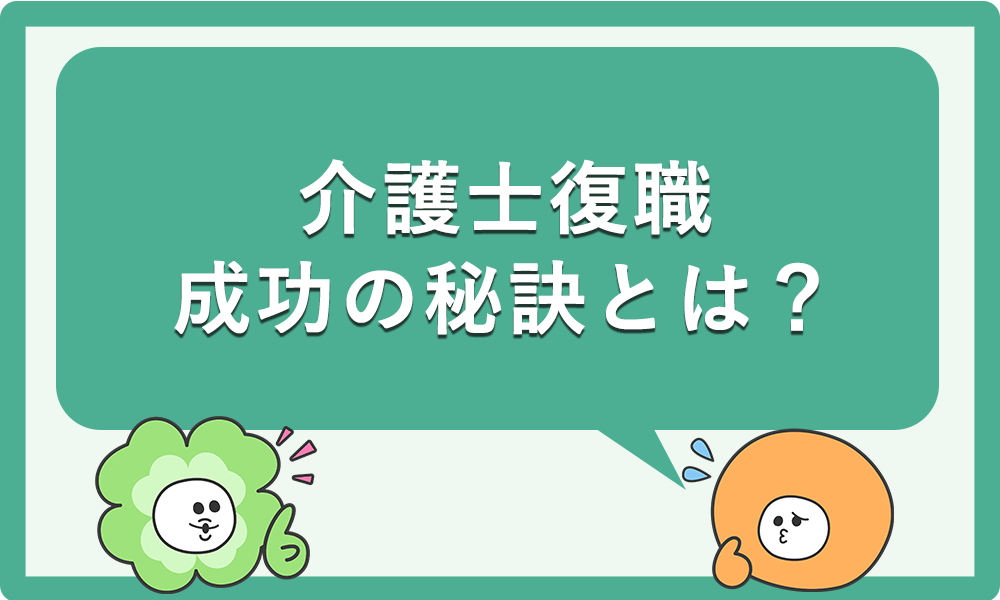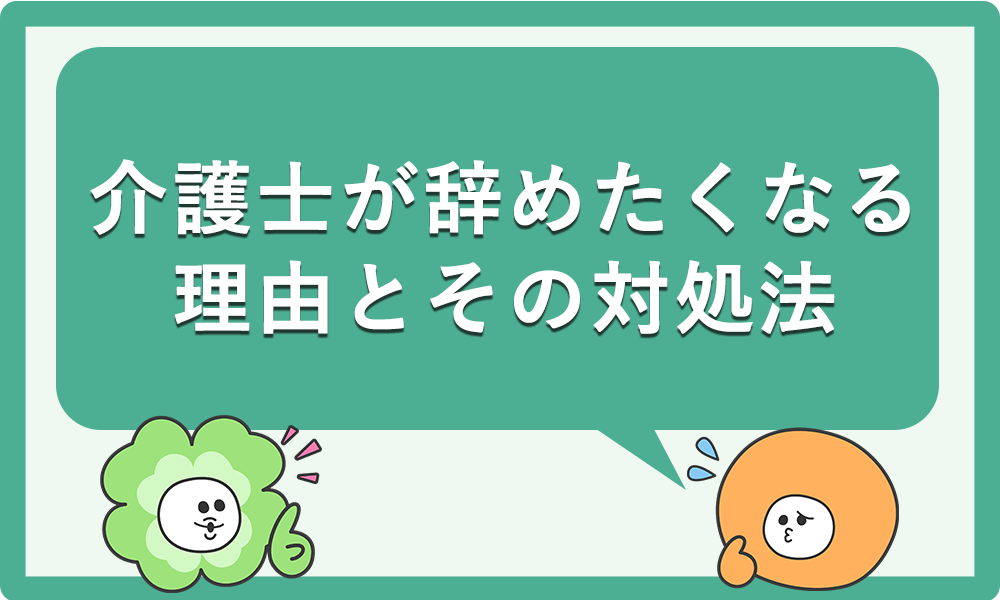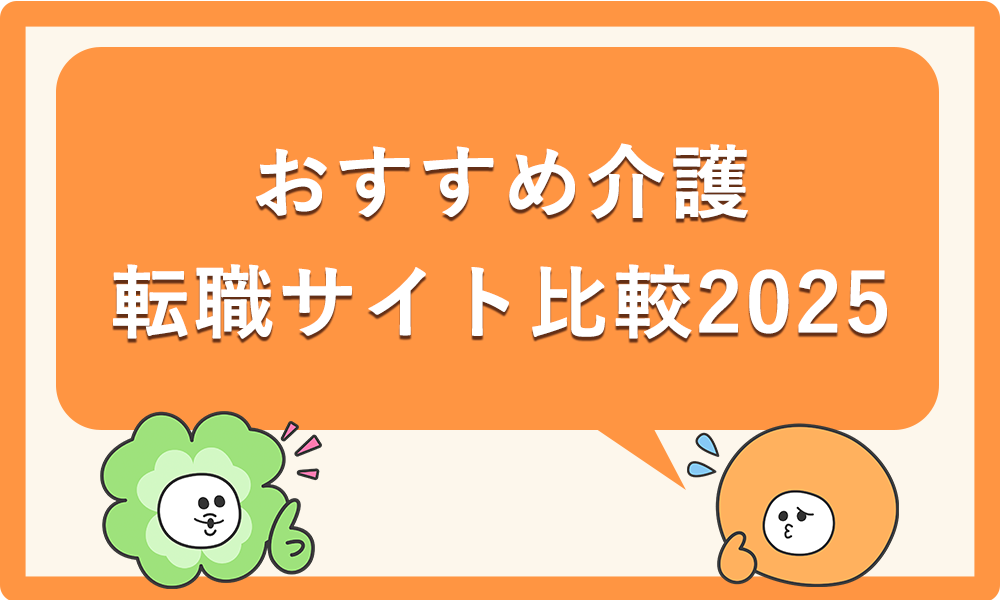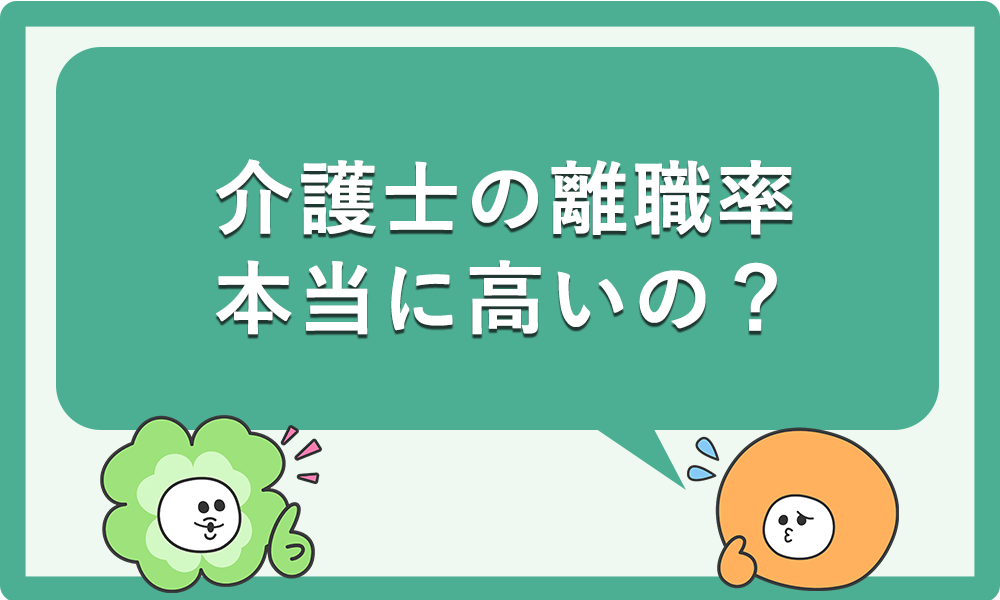
2025/06/11更新
失敗しない!介護士が語る転職理由ランキング、あなたはどれに共感する?
※プロモーションを含みます
-
正直、今の職場のままでいいのか最近迷っちゃうんだよね…
本当にこのままここで仕事をしていて、将来大丈夫なのかな?
-
確かにそうだよね。同じところでやりがい持ってやっていても、迷う時ってあるよね。せっかくだからみんながなんで転職したのか、どうやって転職を決意したのか見てみようよ!

介護の仕事にやりがいを感じている一方で、「今の職場、このままでいいのかな…」と迷う瞬間はありませんか?
人間関係、収入、働き方──日々の積み重ねの中で、小さな違和感がいつの間にか大きな不安へと変わっていくこともあります。
この記事では、実際に多くの介護職の方が転職を決意した理由を、データをもとにランキング形式でご紹介します。
同時に、面接で伝えやすい前向きな転職理由の例や、職場選びで後悔しないためのポイントも解説しています。
今の環境に少しでも不安や不満を感じている方にとって、次の一歩を考えるヒントになれば幸いです。
目次
1. 介護職のよくある転職理由ランキング
介護労働実態調査によると、下記理由で転職を決意した介護士が多いそうです。
- 職場の人間関係に問題があったため
- 法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため
- 他に良い仕事・職場があったため
- 収入が少なかったため
- 自分の将来に見込みがないため
法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため
経営理念や運営に不満を持って転職する方も非常に多くいます。具体的には
- 経営の効率性やリスクを過度に重視しているため、介護の質の向上の取り組みが二の次となっていた
- 介護の質の向上の手法・方向性が自分の理想とは異なっていた
- 無駄な業務が多く職員の業務量負担への配慮が弱かった
- 仕事の仕方に関する職員の提案を、管理者が聞いてくれなかった
このような理由で退職に至っている方が多いです。介護紹介は人手不足が深刻な業界ですが、この状況でも業績を上げるために、
- 利用者の増加を図った施策や方針を立てる
- 給与を上げないまま拡大していく
などの施設が少なからず存在しています。このような環境では、経営方針への不満が高まる一方です。
また、現場で働いている介護士による業務改善のための提案を、上司や上長が承認しない場合や無駄な作業が改善されない場合、一番負担がかかってくるのは現場の介護士になります。このような環境では、不満はどんどん蓄積されていく一方になるでしょう。そのために転職を選ぶ方も多いです。
他に良い仕事・職場があったため
上記二つを理由に、より良い職場に転職するケースもあれば、手に職をつけて就職した方などが当てはまってくるでしょう。
職場の人間関係や経営方針に理解ができず、より理解できる職場を求めて転職を決意する介護士が多い状態となっています。
収入が少なかったため
国として『介護職員処遇改善加算』の創設などが進められており、介護職の給与面改善は様々な施策が取り組まれています。しかし現状は、給与への不満によって転職をする人が多い状態となっています。
この現状の背景には、介護保険事業所の収入の多くが公費で占められており、事業の判断で給与の増額をすることが非常に難しいという問題があります。これでは職場によって給与に差が出てきてしまい、知り合いなどからもっといい条件の話などを聞いて、転職を考えるケースもあるかと思います。
自分の将来に見込みがないため
最後に、介護職が転職を決めた理由は『自分の将来に見込みがないため』です。
これはここまでランキングで挙げた様々な要因がきっかけで、将来が見込めないというケースが多いです。
- 給与が少ないため、将来家庭を持つとなると、今のままだと本当に大丈夫なのか?
- 昇給がない、上の役職が既に埋まっていて、昇進が期待できない
などの理由によって、将来性がとてもなくなってしまい、転職を決意する人がいるのも現状です。
2. 介護職が伝えやすい転職理由例
転職理由や採用担当が注目しているポイントを理解したうえで、具体的にどのような転職理由が好印象を与えるのかを見ていきましょう。主に以下のような理由が挙げられます。
- 自分を成長させられる環境で仕事をしたい
- 施設利用者との接し方、コミュニケーションの取り方を見直したい
- 教育制度や設備の整った施設で働きたい
自分を成長させられる環境で仕事をしたい
介護業界では、業務に対して前向きに取り組み、スキルや知識の向上を目指す人材が歓迎されます。このように、「成長への意欲」が伝わる理由は、面接でも良い印象を与える要素の一つです。
効果的に伝えるには、自分が目指す姿や学びたい内容と、その職場が提供している教育や取り組みとのつながりを具体的に説明すると説得力が増します。
施設利用者との接し方、コミュニケーションの取り方を見直したい
介護職は常に利用者の立場に立ち、相手を思いやりながら業務にあたることが求められます。**利用者との関わり方を改めたいという理由は、**そうした姿勢があることの表れとして、採用担当に好印象を与えやすいです。
前職でどのように利用者と関わっていたか、そこから何を学び、今後どう変わっていきたいのかを具体的に説明することで、より真剣さや誠実さが伝わるでしょう。
教育制度や設備の整った施設で働きたい
「教育制度が整った環境で働きたい」という理由は、一見前向きに見える一方で、受け取り方によっては「受け身な姿勢」と思われてしまう可能性もあります。
3. 介護職の採用担当者に好印象を与える退職理由の伝え方
そのため、重要なのは、自分自身の成長を目指す中で、その手段として整った教育制度を活用したいと考えている、という主体性のある意志を伝えることです。そうすることで、前向きで能動的な転職理由として受け止めてもらいやすくなります。
転職理由を伝える場面は、面接の中でも特に注目されやすいポイントです。特に介護職は、人柄や価値観が重視される職種でもあるため、理由そのものだけでなく、その伝え方が面接官の印象を大きく左右します。
たとえ前向きな理由であっても、言葉の選び方や話す順序によって、誤解を招いてしまうこともあります。
印象よく伝えるためのコツとしては、
- 「ここで働きたい」という気持ちをしっかり持つこと
- 嘘をつかず、正直な気持ちを伝えること
- 退職理由と志望動機に一貫性を持たせること
- 前向きでポジティブな内容にまとめること
などが挙げられます。
ここでは、あなたの本音や志望動機がよりポジティブに伝わるよう、面接での話し方や工夫のポイントを具体的に解説していきます。
「ここで働きたい」という気持ちをしっかり持つこと
最初のポイントは、「この職場で働きたい」という意志をしっかりと持って伝えることです。
「なぜ数ある施設の中でこの職場を選んだのか」「ここで自分が何を実現したいのか」といった問いに自分なりの答えを持っておくことで、面接時の説得力がぐっと増します。
こうした自己分析を行うことで、表面的な理由ではなく、より具体的で本質的な志望動機を掘り下げることができ、思いがけない自分の価値観や目標に気づくこともあります。
介護業界では、仕事に対する真剣な姿勢や意欲が重視されます。そのため、「この職場で働きたい」という熱意を正直に伝えることが、選考を突破する大きな鍵となります。
特に、前向きな理由やポジティブな気持ちを添えて伝えることで、採用担当者により良い印象を与えやすくなります。
嘘をつかず、正直な気持ちを伝えること
転職理由を伝える際に大切なのは、背伸びをせず、自分の気持ちに正直でいることです。
印象を良くしようと、ネガティブな事情を無理に前向きな言葉に変えすぎてしまうと、かえって話に不自然さが出てしまい、「本当のことを話していないのでは?」と疑念を持たれる原因になります。
一貫性のある話し方は信頼感につながります。多少ネガティブな背景がある場合でも、正直に、かつ前向きな姿勢を添えて伝えることで、誠実さや人柄が伝わり、むしろ好印象を与えることができるのです。
相手に納得感を持ってもらうためにも、自分の言葉で素直に語ることが大切です。
退職理由と志望動機に一貫性を持たせること
面接で退職理由を話す際には、前の職場で感じた課題や物足りなさと、次に目指す環境や理想をうまくつなげて説明することがポイントです。
たとえば、「以前の職場では業務が非常に忙しく、利用者一人ひとりに丁寧に関わる時間が取りづらかった」という退職理由がある場合には、「こちらの施設では、利用者との関係づくりに時間をかけられる体制が整っており、自分の理想とする介護ができると感じました」といったように、退職の背景と志望理由がつながるように話すと自然です。
転職後にどのような姿を目指しているのか、具体的な成長イメージや目標もあわせて伝えることで、面接官に「この人は明確なビジョンを持っている」と好印象を与えることができるでしょう。
前向きでポジティブな内容にまとめること
転職理由を伝える際は、なるべく前向きな表現を心がけることが大切です。
誰しもが何らかの不満や課題を感じた結果として転職を考えるものですが、面接官はその背景だけでなく「そこから何を学び、どう前向きに行動しようとしているのか」に注目しています。
ネガティブな感情をそのまま伝えるのではなく、「その経験を通じて何に気づいたか」「次の職場ではどのように改善していきたいか」といった、前向きな視点に変えて伝えることで、より仕事への意欲や成長意識を感じてもらえるでしょう。
たとえ本音がマイナスの感情であっても、嘘をつく必要はありません。大切なのは、正直な気持ちを前向きに捉え直し、ポジティブなメッセージとして届ける姿勢です。
4. 介護の職場選びに失敗しないために
介護の仕事を長く続けていくためには、「働きやすさ」や「自分に合っているかどうか」をしっかりと見極めることが大切です。条件が良さそうに見えても、自分の希望と合っていなければ後悔する可能性もあります。
転職活動の際には、以下のようなポイントを基準に、職場を比較・検討してみましょう。
下記のような項目は特に確認しておくのがおすすめです:
- 職場の人間関係:スタッフ同士の雰囲気や、チームワークの取りやすさ
- 給与:希望する収入に見合っているか、昇給・賞与制度の有無
- 勤務体制や休暇:シフトの柔軟さ、休日数、有給の取りやすさ
- 通勤時間や距離:通いやすさ、交通費の支給、マイカー通勤の可否
これらのポイントを自分なりに優先順位づけしておくことで、複数の求人があった場合にも判断しやすくなります。求人情報だけでは分かりにくい部分は、見学や面接で直接確認してみるのも良いでしょう。
職場の人間関係
介護の現場では、スタッフ同士の連携や協力が欠かせません。そのため、職場内の人間関係が良好かどうかは、長く働くうえでとても重要なポイントです。
実際、人間関係が原因で転職を考える人は多く、介護職の退職理由としてもよく挙げられています。ただし、人間関係の良し悪しは求人情報だけでは判断しづらいのが現実です。
そこでおすすめなのが、事前に職場見学をしてみること。実際に職場の雰囲気を感じたり、スタッフの様子を観察したりすることで、自分に合いそうかどうかを見極めやすくなります。
「どんな人たちが働いているのか」「スタッフ同士のやり取りはスムーズか」などをチェックすることで、ミスマッチを防ぐ一助になるでしょう。
給与
職場選びで重要なポイントのひとつが、「給与や福利厚生が充実しているかどうか」です。給与が高いに越したことはありませんが、福利厚生とのバランスもよく確認しておくことが大切です。
介護施設の経営形態には、株式会社や社会福祉法人など様々な種類があります。それぞれの特徴を理解することが、働き方や給与の見通しを把握するうえで欠かせません。
株式会社の場合、営利を目的としているため、役職に就くことで給与が増えるケースが多いですが、役職がつかない場合は大きな昇給は期待しづらいのが実情です。
一方、社会福祉法人は国からの助成金が支給されるため、役職昇進がなくても安定した給与が期待できる傾向があります。
そのため、自分が働きたい職場の経営形態や給与体系を事前にしっかり確認しておくことが重要です。
勤務体制や休暇
介護の勤務形態は、働く施設の種類によって大きく異なります。例えば、訪問介護を選ぶ場合は主に日中の勤務が中心となりますが、特別養護老人ホームなどの施設勤務の場合は、早番・遅番・夜勤を含む24時間体制でのシフト勤務が求められます。
自分が希望する働く時間帯や勤務スタイルを明確にし、その条件に合った勤務体制を持つ職場を選ぶことで、実際に働き始めてから勤務時間や働き方のミスマッチに悩むリスクを減らせます。
また、労働時間や休暇の取りやすさは、日々の仕事の質や生活のバランスに大きく影響します。無理のない働き方ができるかどうか、勤務時間や休日数の詳細をきちんと確認することが大切です。
通勤時間や距離
職場選びで重要なポイントの一つに「通勤時間の長さ」があります。
介護の仕事は体力を多く使うため、通勤に時間がかかりすぎると、それだけで疲れがたまってしまい、仕事自体がさらに大変になることがあります。
特に、夜勤がある施設、例えば特別養護老人ホームなどでは、公共交通機関が利用できない時間帯があることも考えられます。
そのため、居住地から近く、通勤時間が短い職場を選ぶことが望ましく、できるだけ通勤による体力消耗を抑えることが、仕事に集中するうえで大切です。
また、自転車や徒歩でも通勤可能な距離にある施設は、体力的な負担を減らすためにも優先的に検討すると良いでしょう。
5. まとめ
介護職の転職理由ランキングを押さえる
多くの介護士が「人間関係」や「経営方針・雰囲気」「収入」「将来性」に不満を抱えて転職を選んでいます。自分も当てはまるかチェックしてみましょう。
面接で伝えるべき理由は「ポジティブ」で「一貫性のある」内容に
- 成長意欲が伝わる理由を用意する
- 利用者との関わり方を改善したいという志望動機を整理する
- 教育制度を自ら活用する姿勢を見せる
これらを「ここで働きたい」という気持ちとつなげ、熱意と誠実さを伝えることが効果的です。
職場選びでは、“ミスマッチを防ぐ視点”で判断を
- 人間関係:職場見学やスタッフとのコミュニケーションで肌感をつかむ
- 給与・福利厚生:株式会社か社会福祉法人かによる収入構造の違いを理解する
- 勤務体制・休暇:24時間体制が希望ならシフトや夜勤体制を要確認
- 通勤時間・距離:体力温存の観点から、自宅から近距離の職場を優先視野に