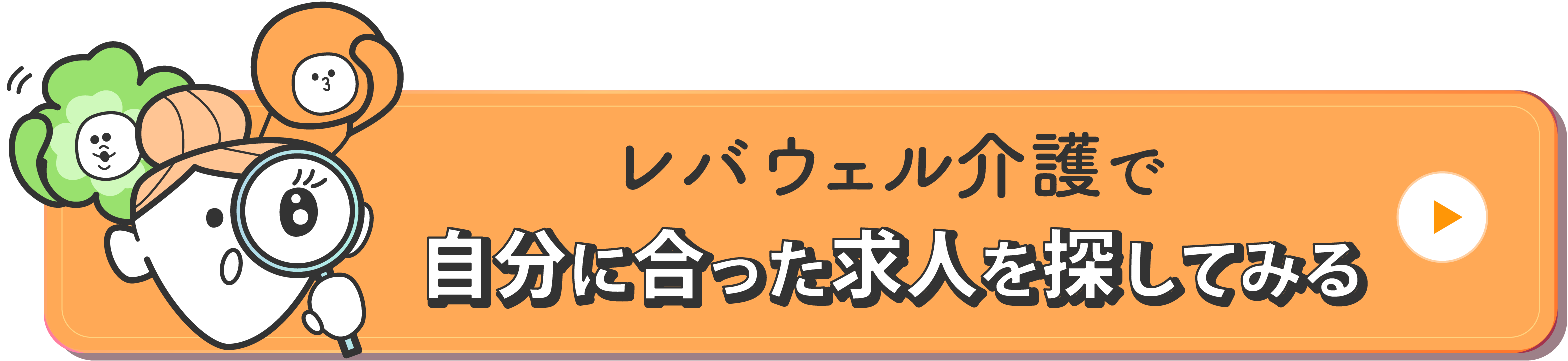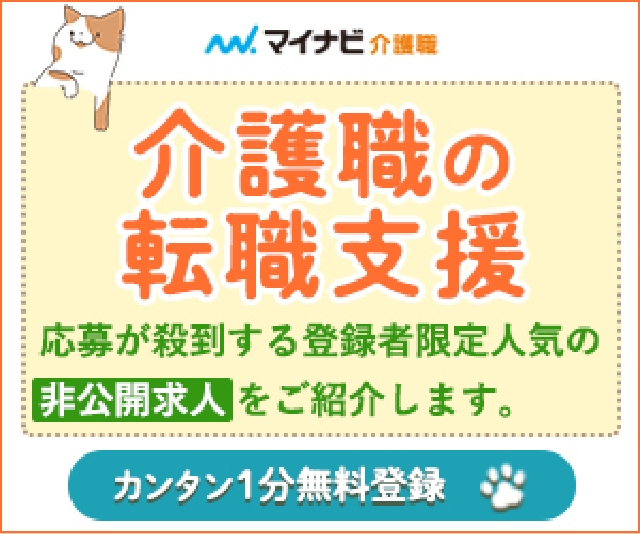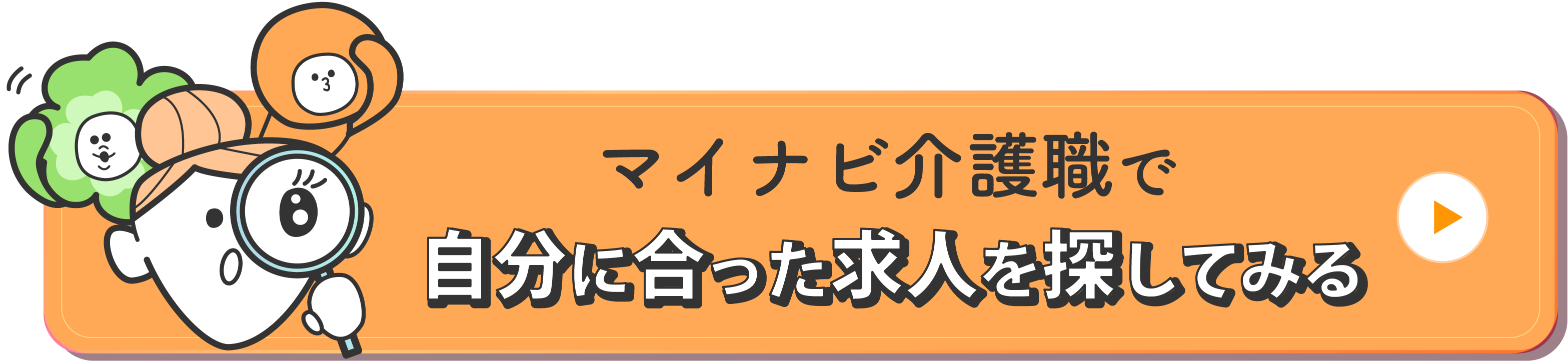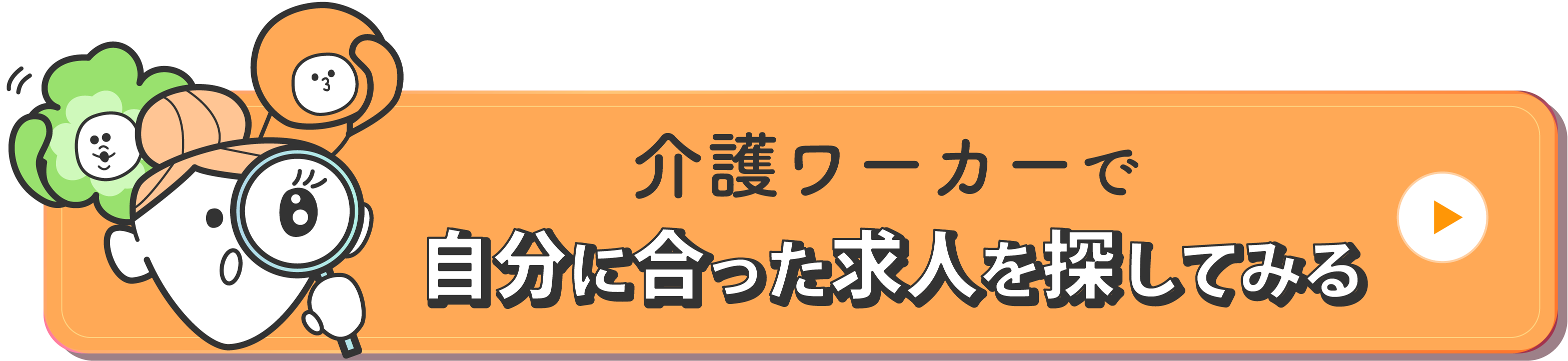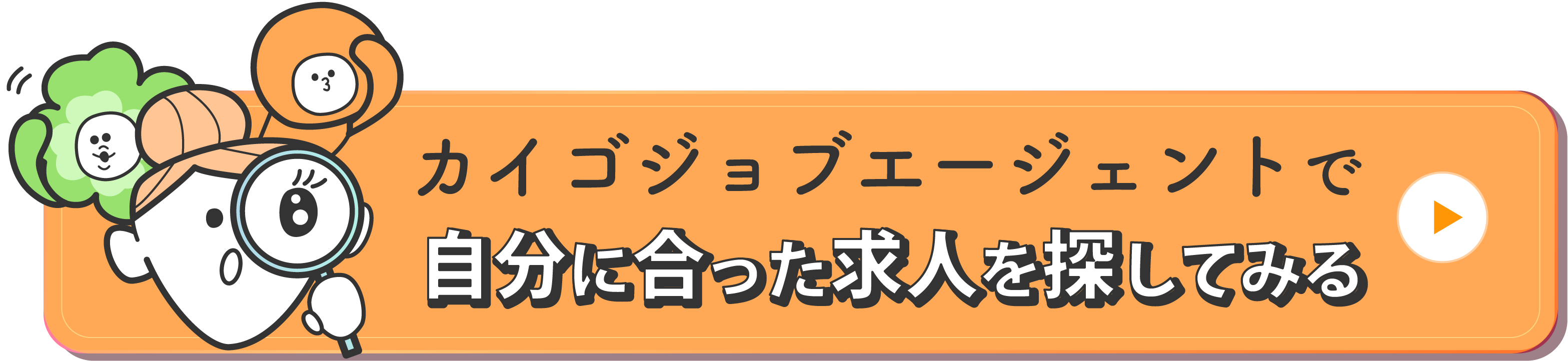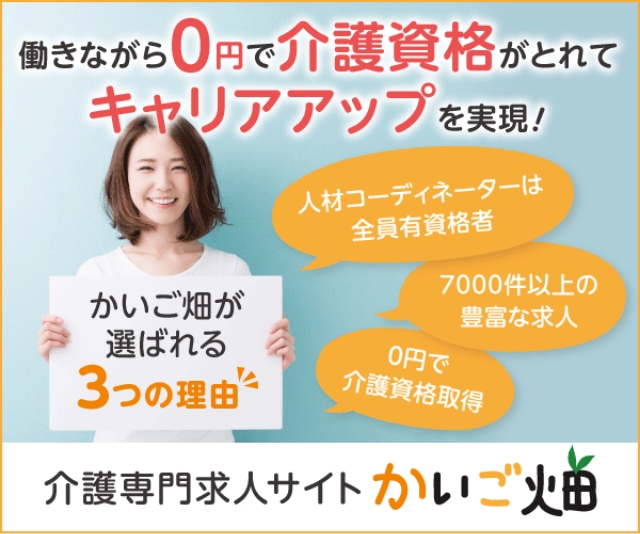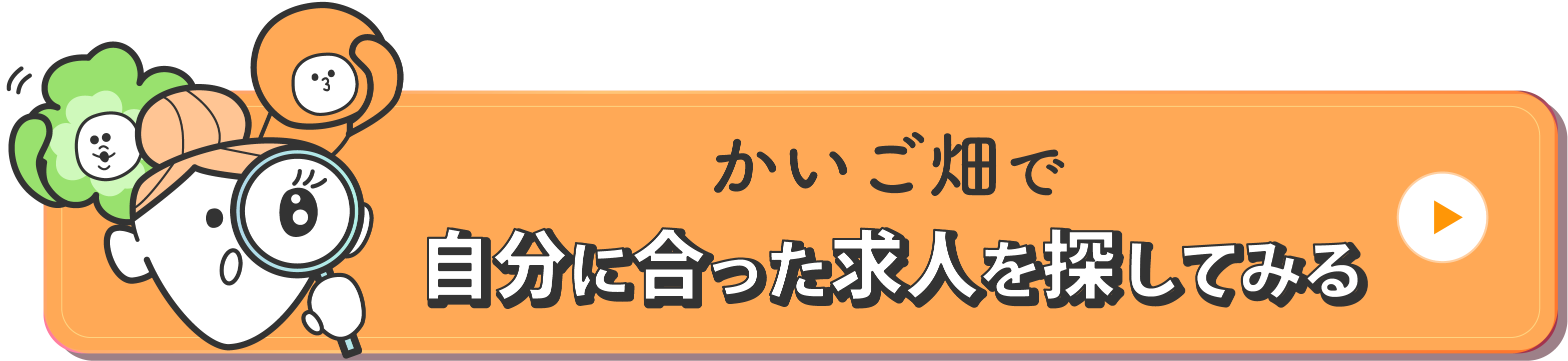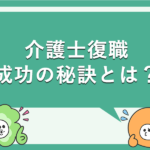2025/06/26更新
後悔しない!介護士が活用すべき年収アップに役立つ情報
※プロモーションを含みます
-
介護士として年収上げていきたんだけど、どうやったら年収って上がっていくの?

-
実際に少しずつ上昇傾向にはあるけど、どうすればいいのか一緒に見てみよう!!

介護職の給与は、処遇改善加算などの影響で少しずつ上昇傾向にあります。しかし、雇用形態や資格、地域、施設の種類によってその差は大きく、すべての介護職員に平等とは言えません。
本記事では、最新の統計データをもとに、介護職の給与推移や職種・地域ごとの相場、収入を伸ばすための具体策までをわかりやすく解説します。
目次
1. 介護職の平均給与の推移と相場感
介護職の給与は、働き方や資格、地域、施設の種類など多様な要素によって変動します。近年は介護従事者の処遇改善に向けた施策も進められ、平均給与も徐々に上昇傾向にありますが、その実態は一様ではありません。
本章では、常勤・非常勤、月給制・時給制を含めた給与の推移データをはじめ、職種別・施設形態別・地域別の給与相場を詳しく見ていきます。これにより、ご自身のキャリアや希望に合った給与水準の目安をつかんでいただければ幸いです。
月給制の平均給与の推移
介護職の常勤職員における月給の平均は、ここ数年で着実に上昇傾向を見せています。具体的には、2018年から2024年の6年間で、およそ4万円近くの増加が確認されています。これは、処遇改善加算や補助金制度などの政策的な後押しが要因とされており、継続的な待遇改善の成果が数値にも表れています。
以下は、厚生労働省による調査に基づいた、常勤・非常勤それぞれの平均月給の推移です(※加算取得状況に基づく事業所対象):
調査年 常勤平均(月給)と非常勤平均(月給)
- 2024年 338,200円 196,060円
- 2023年 324,240円 182,930円
- 2022年 317,540円 209,540円
- 2021年 316,610円 198,520円
- 2020年 315,850円 196,630円
- 2019年 300,120円 189,200円
- 2018年 300,970円 209,470円
出典:厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査 結果の概要」他(令和6年度調査P.126 ほか)
このデータからもわかるとおり、常勤職員の給与は一貫して右肩上がりである一方、非常勤職員については年によって増減が見られることも特徴です。これは、勤務日数や時間数などに左右されやすい非常勤の雇用形態に起因していると考えられます。
また、勤務先の法人種別(民間・社会福祉法人など)や施設形態(特養・有料老人ホーム・訪問介護など)によっても、実際の給与額にはばらつきがあるため、相場を把握するうえでは自分が目指す働き方に応じたデータの確認も重要です。
パート・時給制の平均給与
介護業界におけるパート職員の時給水準は、近年少しずつ上昇傾向にあります。とくに、処遇改善施策の影響を受けやすい常勤パートの時給は、2018年から2024年までの6年間でおよそ224円増加しており、これは介護報酬の引き上げや各種加算の効果が着実に現れている証左といえるでしょう。
以下に示すのは、常勤および非常勤パート職員の平均時給の推移です(加算制度を取得している事業所を対象とした厚労省の調査データより):
調査年 常勤パート時給(平均)と非常勤パート時給(平均)
- 2024年 約1,515円 約1,542円
- 2023年 約1,434円 約1,469円
- 2022年 約1,376円 約1,386円
- 2021年 約1,359円 約1,398円
- 2020年 約1,344円 約1,370円
- 2019年 約1,289円 約1,318円
- 2018年 約1,291円 約1,333円
出典:厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査 結果の概要」ほか(令和6年度調査P.128 など)
この時給額は、各パート職員の実労働時間をもとに月給から換算された値です。常勤パートでは、おおむね年間を通じた勤務実績がある職員を対象にした平均であり、継続的な雇用を背景とした給与改善が進んでいることが読み取れます。
一方で、非常勤パートに関しては、年ごとにばらつきがあるのも実情です。これは勤務時間の長短や雇用形態の柔軟性が影響しており、同じ時給制でも状況によっては収入水準に差が出やすい構造があるためです。
なお、地域による最低賃金の違いや、施設の運営方針、加算取得の有無によっても時給相場には幅が生じます。そのため、これらの数値は全国的な目安として把握しておくのがよいでしょう。
職種別の平均給与(介護福祉士、初任者研修など)
介護施設に勤務するスタッフの給与は、担当する業務内容や職種によって異なります。以下は、月給制・常勤雇用の職員に限定した職種別の平均月収データです。
職種と平均月収(常勤・月給制)
- 介護職員 約315,850円
- 看護職員 約379,610円
- 生活相談員・支援相談員 約343,310円
- 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員 約358,560円
- ケアマネジャー(介護支援専門員) 約357,850円
- 事務職員 約311,120円
- 調理スタッフ 約267,930円
- 管理栄養士・栄養士 約319,680円
※出典:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果」(P.128)
この統計からもわかるように、医療系専門職(看護職員やリハビリ職)や相談支援職は比較的高めの給与水準となっており、それに対して介護職員はやや低い傾向にあります。ただし、介護職員も資格の有無や等級によって待遇に差が生じるため、無資格者と介護福祉士などの国家資格保持者では支給額に開きがある点には注意が必要です。
たとえば、介護福祉士を取得している職員は、基本給や資格手当が加算されやすく、同じ業務をこなすなかでも高めの報酬が見込まれます。一方、初任者研修のみの人や無資格の職員は、給与水準は控えめになりがちです。
このように、職種別に見ると給与水準にバラつきがあるため、将来的なキャリアアップや収入改善を見据えて、資格取得を検討することは有効な選択肢となるでしょう。
雇用形態別・施設形態別の違い
介護職の給与水準は、勤務形態や配属先の施設種別によっても大きく変動します。
【施設形態ごとの平均給与】
常勤で働く介護職員を対象にした調査結果では、以下のように施設種別ごとに平均月収に差が見られます。
施設種別と平均月給(常勤・月給制)
- 介護老人福祉施設 約350,430円
- 介護老人保健施設 約338,920円
- 介護療養型医療施設 約306,420円
- 介護医療院 約312,600円
- 訪問介護事業所 約306,760円
- 通所介護事業所 約280,600円
- 通所リハビリテーション事業所 約305,660円
- 特定施設入居者生活介護事業所 約322,020円
- 小規模多機能型居宅介護事業所 約287,980円
- 認知症対応型共同生活介護事業所 約287,770円
(出典:厚生労働省「令和2年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.131)」)
身体介助の負担が大きいとされる入所系の施設では、平均賃金がやや高めに推移している傾向があります。これは、業務の負担感や専門性の高さが給与に反映されているためと考えられます。
【雇用形態による給与差】
一方、雇用形態によっても収入には大きな差が出ます。
厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によれば、常勤職員の平均給与は322,550円であるのに対し、非常勤職員の平均は204,440円と、およそ12万円の開きがあることが分かっています。
また、同じ職種でも、勤務形態によって報酬水準は異なります。たとえばケアマネジャー(介護支援専門員)の場合:
常勤ケアマネジャー:365,180円
非常勤ケアマネジャー:299,250円
というように、常勤の方が高水準となっており、資格を持つ専門職であればさらに高額な給与が見込まれる状況です。
(参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果(p.269)」)
このように、給与面での安定性や将来的な昇給を考慮すると、常勤雇用やキャリアアップを視野に入れた資格取得が重要な要素となるでしょう。
都道府県別の給与ランキング
介護職における年収は、全国一律ではなく、地域ごとの経済状況や物価水準、人材需給のバランスなどに応じて差が出るのが実情です。とくに、施設勤務の介護職員の平均年収は、都道府県ごとに大きく異なる傾向が見られます。
以下は、全国47都道府県の中で上位に位置する地域の平均年収データです(施設勤務の介護職員を対象)。
都道府県と平均年収
- 1位 広島県 約404万1,800円
- 2位 東京都 約394万7,400円
- 3位 神奈川県 約392万1,600円
- 4位 千葉県 約391万6,700円
- 5位 愛知県 約388万7,100円
(出典:厚生労働省「令和5年賃金構造基本統計調査」)
この調査では、広島県が唯一400万円台を超え、最も高い平均年収を記録しています。加えて、同県では賞与額も他県より高めであり、年収全体の底上げにつながっています。
また、上位に並んだ地域はいずれも都市圏に集中しており、都市部では賃金が高水準に保たれている一方で、地方圏では相対的に低くなる傾向があることがわかります。
給与水準の地域格差は、介護職への就職・転職を考える上での一つの判断材料となるでしょう。
資格別・勤続年数別の年収相場
介護職における年収水準は、保有している資格の種類や実務経験の長さによって大きく左右されます。業務の専門性が増すほど、任される役割の幅が広がり、それに比例して給与水準も上昇する傾向にあります。
以下は、「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」に基づく、有資格者ごとの月給平均です(常勤・月給制の場合):
- 介護支援専門員(ケアマネージャー):約37万6,240円
- 介護福祉士:約33万1,690円
- 社会福祉士:約35万2,560円
- 実務者研修修了者:約30万250円
- 介護職員初任者研修修了者:約30万2,910円
(参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果 p.232」)
このデータからもわかるように、より専門性が高い資格を有する人ほど、平均月収が高い傾向にあることが読み取れます。とくに、ケアマネージャー(介護支援専門員)は、他の資格と比べて業務範囲が広く、利用者のケアプラン作成など責任あるポジションを担うため、給与面でも優遇されやすい職種です。
また、介護職においては、資格だけでなく勤続年数も収入に大きな影響を及ぼします。長く働くことで、処遇改善加算などの対象になりやすくなるほか、昇給や役職手当といった面でも待遇改善が期待されるでしょう。
2. 給与アップを狙える働き方とは?
給与アップを目指す介護職の方にとって、働き方や職場選びは重要なポイントです。単に基本給が上がるのを待つだけでなく、手当の活用や勤続年数、転職先の選択、福利厚生の充実度など、多角的な視点で収入向上を図ることが可能です。
この章では、介護職が実際に給与アップを狙いやすい具体的な方法について、効果的な働き方や職場の特徴を詳しく解説します。ぜひ自分の状況に合った選択肢を見つけて、賢く収入を伸ばしていきましょう。
夜勤手当を活用する
介護職の給与を高めたい場合、夜勤に積極的に入ることが一つの有効策となります。夜間勤務には、通常の賃金とは別に「夜勤手当」や「深夜割増賃金」が支給されるため、働き方次第で収入アップが見込めます。
実際に、レバウェル介護が実施した調査によれば、夜勤手当が設定されている職場では、約6割の職員が1回あたり5,000~8,999円の手当を受け取っていることが分かっています。夜勤の頻度としては、月に5~6回が平均的で、体力的に余裕がある方は勤務回数を調整することで収入を底上げすることが可能です。
また、「夜勤専従」という働き方を選べば、勤務するたびに夜勤手当が加算されるため、少ない出勤日数でも一定の収入を得やすいという利点があります。
ただし、夜間帯の勤務は生活サイクルが崩れやすく、体調管理が難しくなるケースも少なくありません。無理のない範囲でシフトを組み、健康面にも配慮しながら働くことが重要です。
さらに、夜勤手当は法的に明確な金額基準が設けられておらず、事業所ごとに設定されているため、勤務先によって支給額に差が出る点にも注意が必要です。
長く勤めて評価・昇給を得る
介護職員の給与は、勤続年数が長くなるにつれて上昇する傾向があります。厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(p.146)によれば、勤続1~4年の介護職員の平均給与は311,880円、5~9年では335,640円、そして10年以上勤めている場合は359,040円に達しています。特に、10年以上勤務する職員は1~4年の職員に比べて約5万円ほど高い収入を得ていることがわかります。
給与の昇給制度が整っている職場であれば、長く勤務を続けることで安定的に収入アップが期待できます。また、同じ職場で長期間働くことは、利用者との信頼関係の構築や専門的なスキルアップ、さらにはキャリアの向上にもつながるメリットがあります。
<H3> 給与が高い施設に移る
現在の勤務先で給与の伸びが見込めない場合は、給与がより高い職場へ転職することも選択肢の一つです。転職の際は、基本給だけでなく手当や賞与の内容も含めて総合的に条件を比較することが重要です。また、応募前に処遇改善加算を導入しているかどうかも確認しておくと良いでしょう。詳しいポイントは、「【介護】転職で年収アップは可能?給与アップのポイントとリスクを解説」で解説されていますので、参考にしてみてください。
介護施設の給与は、経営状況や地域差によって大きく変わります。経営が赤字の施設では給与アップが難しいのに対し、黒字運営の施設では比較的給与が上昇しやすい傾向があります。加えて、都道府県ごとの賃金差も存在し、都市圏では介護職の給与が高めに設定されている場合が多いです。現在の給与に不満があるなら、給与の高い施設や地域への転職を検討するのも有効でしょう。
ただし、給与だけでなく福利厚生や職場環境も含めて総合的に判断し、より良い条件の職場を選ぶことが大切です。
福利厚生や住宅手当が充実している事業所に注目
福利厚生や各種手当が充実している介護施設に転職すると、基本給が変わらなくても年間の収入が増える可能性があります。具体的な手当には、住宅手当や家族手当、家賃補助などがあり、たとえば毎月2万円の住宅手当が支給されれば、年間で約24万円のプラスとなります。給与だけでなく、こうした手当や利用可能な福利厚生制度にも注目しながら転職先を選ぶことが重要です。
また、介護事業所によっては生活面の支援が手厚い福利厚生が整っている場合があります。よく見られる福利厚生には、健康保険や厚生年金、介護保険などの社会保険、通勤手当、食事補助、住宅手当、退職金制度、特別休暇、産休・育休、資格取得支援制度などが挙げられます。こうした制度がしっかりしている職場は、安心して長く働ける環境と言えるでしょう。
さらに、施設独自の福利厚生として医薬品の割引や予防接種のサポートなどがある場合もあるため、応募前に確認しておくことをおすすめします。
3. 転職で年収アップを狙う戦略
介護職として年収アップを目指すなら、ただ単に転職するだけでなく、戦略的に職場を選ぶことが重要です。施設の評価制度や給与体系、福利厚生の充実度など、多様な観点から転職先を見極めることで、より良い条件での採用を目指せます。ここからは、年収アップに役立つ具体的なポイントを紹介します。
実力や経験を評価する職場を探す
施設によっては年功序列型の評価制度を採っており、転職によってかえって年収が下がってしまうケースも少なくありません。こうした環境では、スキルや経験よりも勤続年数が重視されるため、転職先での待遇が思うように上がらない可能性があります。
その一方で、実力を正当に評価してくれる施設へ移ることで、資格や経験を活かした年収アップが期待できる場合もあります。とくに、初任者研修や実務者研修を修了していれば、即戦力としての評価が得られやすく、転職時のアピール材料にもなります。
資格取得によって選べる施設の幅が広がるだけでなく、実力重視の職場への転職成功率を高める効果もあるため、長期的な収入向上を見据えたキャリア戦略として有効です。
給与水準が高い施設形態(特養・老健・訪問など)を選ぶ
現在の職場で給料のアップが期待できない場合、給与水準の高い施設へ転職することも有効な選択肢です。転職を検討する際は、基本給だけでなく各種手当や賞与の有無も含めて、総合的に条件を比較することが重要です。さらに、応募前にその施設が処遇改善加算を取得しているかどうかを確認しておくこともポイントになります。詳しくは、「【介護】転職で年収アップは可能?給与アップのポイントとリスクを解説」などの情報も参考にしてください。
介護報酬は定められていますが、「介護職員処遇改善加算」の対象となっている施設は、給与設定が比較的高めである可能性があります。この加算は介護職員の待遇向上を目的としており、5つの区分に分かれていて、取得区分に応じた金額が施設に支給されます。例えば、「加算I」を受けている場合、1人あたり月額約37,000円相当の加算が施設に入ります。加算の配分方法は施設によって異なりますが、取得施設は給与が高い可能性があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
また、介護施設の給与水準は経営状態や地域差にも大きく左右されます。経営が厳しい施設では給与の上昇が難しいのに対し、黒字運営の事業所は比較的昇給しやすい傾向があります。加えて、都市部は地方に比べて介護職の給与水準が高い傾向にあるため、現状の給与に不満がある場合は給与が良い地域や施設を検討するのも効果的です。給与だけでなく福利厚生や労働環境の面も考慮し、トータルで満足できる職場を選ぶことが大切です。
福利厚生や賞与制度を比較する
給与額そのものが変わらなくても、手厚い福利厚生や各種手当が充実している職場に転職することで、結果的に年収アップが期待できます。例えば、住宅手当や家族手当、家賃補助などの手当がしっかりしている場合、月に2万円の住宅手当が支給されれば年間で約24万円の収入増につながります。転職を検討するときは、給与だけでなくこうした手当や福利厚生の内容にも目を向けることが大切です。
介護施設や事業所によっては、生活の質を高めるために多様な福利厚生が整っています。代表的な福利厚生には、健康保険や厚生年金、介護保険などの社会保険、通勤手当、食事補助、住宅手当、退職金制度、特別休暇、産休・育休、資格取得支援制度などがあります。
これらの手当や制度が充実している事業所であれば、安心して長期間働き続けやすくなります。また、医薬品の割引や予防接種の支援など、施設独自の福利厚生を用意しているところもあるため、応募前にしっかり確認しておくと良いでしょう。
管理職・リーダー職での採用を目指す
介護施設で役職に就くことは、給与アップを狙う有効な手段のひとつです。施設長や管理者などの管理職になると、役職手当が付与されたり基本給が上がったりして、収入が増加します。厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(p.143)によると、管理職の平均給与は378,110円で、非管理職の327,720円と比べて約5万円高くなっています。
管理職の仕事は責任が伴いますが、新人指導や施設運営といった介護現場では経験できない業務を担い、やりがいも大きいものです。なお、管理者ポジションには経験年数や資格といった条件を設けている施設もあります。管理職を目指す方は、「介護施設で管理者になるには何が必要?資格要件や仕事内容を解説」といった情報を参考にするとよいでしょう。
4. 給与アップを狙う際の注意点・リスク
収入を増やすことを目的とした転職は、介護職としての働き方を見直すきっかけになりますが、給与だけに注目しすぎると、思わぬ落とし穴にはまってしまうこともあります。たとえば、給与水準が高い職場でも、業務量が多くプライベートの時間が取りづらかったり、面接時の発言が原因で採用を逃してしまったりと、見落としがちなリスクが潜んでいます。
ここでは、給与アップを目的とした転職で陥りやすい注意点や、見極めるべきポイントについて解説します。収入面の向上だけでなく、長く安心して働ける環境を選ぶための視点を持つことが、転職成功のカギとなります。
高収入=業務量が多い・負担が大きい可能性も
年収アップを第一に考えた転職は、仕事とプライベートのバランスを崩すリスクがあります。給与が増えても、長時間労働や夜勤の頻度が高く、休みが取りにくい環境では、身体的な負担が大きくなり、長期間続けることが難しくなるケースもあります。収入だけでなく、勤務時間や働きやすさなどの条件も十分に確認したうえで転職先を選ぶことが大切です。
面接時に年収ばかり聞くと印象が悪くなることも
面接で給与条件ばかりを強調すると、「この人は年収さえ高ければどこでもいいのでは」と受け取られてしまい、採用側に不信感を与える可能性があります。さらに、「より条件の良い職場があればすぐに転職してしまうのではないか」と懸念され、定着性に疑問を持たれることにもつながりかねません。
介護業界に限らず、多くの施設では長期的に働ける人材を重視しています。そのため、転職理由として年収アップを求める姿勢があったとしても、面接時にストレートに伝えるのは避け、働き方やキャリアアップへの意欲などと結びつけた前向きな伝え方に工夫することが大切です。
規模が大きい施設でも給料が高いとは限らない
大手法人や大規模な介護施設への転職を検討する際、「規模が大きい=給与が高い」と思いがちですが、必ずしもそうとは限りません。職員数が多い分、評価制度が一律になりやすく、個々の成果が給与に直結しづらいという側面もあります。また、ポジションや昇給の機会が限られることから、長く働いていても給与面での伸び悩みを感じるケースもあるでしょう。
一方で、中小規模の施設ではスタッフ一人ひとりの貢献が目立ちやすく、それが評価や処遇に反映されやすい傾向があります。転職先を選ぶ際は、施設の規模だけで判断せず、評価体制やキャリアアップのしやすさといった点も含めて総合的に見極めることが重要です。
5. まとめ:処遇改善を味方につけて、介護職で安定収入を目指そう
2025年現在、政府による処遇改善政策や加算制度の刷新により、介護職の給与は緩やかに上昇傾向にあります。特に常勤の介護福祉士や夜勤を担う職員、加算取得率の高い施設などでは、確実に賃金水準が改善されている実態が見えてきています。
一方で、その恩恵をどれだけ受けられるかは、以下のような**「働く場所」や「働き方」の選択**によって大きく異なるのも事実です。
- ✅ 給与改善が進む施設(加算Ⅰ〜Ⅳを取得)を選ぶ
- ✅ 正社員・常勤雇用での就労を目指す
- ✅ 介護福祉士などの資格取得で専門性を高める
- ✅ 夜勤や役職手当などの加算を活用する
- ✅ 給与水準が高めの都市圏や法人を検討する
「給料は本当に上がるのか?」という問いに対しては、「制度と職場を上手に選べば、上がる可能性は高い」というのが現実的な答えと言えるでしょう。
これから介護の仕事を始める方や、転職・キャリアアップを考えている方は、待遇や制度の動向をしっかり把握したうえで、戦略的な選択を行うことがますます重要になっていきます。